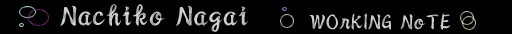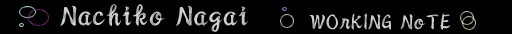ヴィクトリア・ストリートを横切りながら、クラリッサ・ダロウェイは思う。
このすべてのなかに、私の愛するものがある。
人生、ロンドン、6月のこの瞬間・・・なぜ人がこれほど人生を愛するのか、誰も知らない・・・
彼女には、ライフデザイン家の夫と美しい一人娘、アッパークラスの満ち足りた暮しがある。今夜はパーティー・・・首相まで出席するダロウェイ家のパーティー・・・そして彼女は華麗なるホステス役だ。
その時、ビッグ・ベンの鐘の音が響き渡り、それは鉛の輪の波紋となって、ロンドンの空に彼女の微かな不安のように広がっていく。
彼女は、娘の家庭教師に対する不満や、すでに自分は52歳なのだという老いの自覚、そしてスペイン風邪による心臓の後遺症からくる健康の翳りを思い出す。
クラリッサはロンドンの1等地、王様のお膝元にあるウエストミンスターの自宅を出て、ヴィクトリア・ストリートを横切り、セント・ジェームズ公園を通ってグリーン・パークの角からピカデリー、そしてボンド・ストリートへと入っていく。
彼女はボンド・ストリートのマルベリー花店へと向かいながら、ふと空しさを覚えて立ち止まる。
「ミセス・ダロウェイというこの存在、すでにクラリッサですらない、ミセス・リチャード・クラリッサというだけの存在・・・」
「私という人間」は、「私の人生」とは、いったい何だろう・・・
同じ朝、華やかな彼女とはかけ離れた世界に、心を病んだ1人の青年がいる。
彼は、スズメがギリシャ語で歌い、犬が人間に変わり、赤い花が自分の肉体を貫いて成長する幻想に悩まされながら、リージェント・パークに座っている。
第1次世界大戦で親しい同胞を失った・・・彼らは同性だが心から愛し合っていた。
愛する者の死を目の当たりにした時から神経を病み、現実に生きている実感がない。何も感じないということの恐怖が常に襲い続ける。
彼は妻の忠告に従って著名な医師のもとを訪ねるが・・・青年は何かから逃げるように、窓の外に広がる6月の空に飛び出してしまう。
死ぬことの恐怖より、生きることの恐怖に耐えかねて・・・
彼の自殺の報は、クラリッサのパーティーに出席していた医師の口から世間話として伝えられる。
彼女はそれを聞いて、生きることで汚されていく人生をその見知らぬ青年は死をもって守ったのだと思う。しかし彼女は、向かいの家の窓の中に、年老いた女性がベッドに入ろうとしている光景を見て、人生をまっとうすることもまた魅力的だと感じる。「人生」とは、「生きること」とは本当に興味深いことなのだ。
この晴れやかな6月の今日という日の背後に、すべての過去へと続く迷路のような洞窟がある。
遠く過ぎ去った時間・・・クラリッサは青春の記憶を辿り始める。
恋人のピーターを捨てて今の夫と結婚することを決め、もう一方では素敵な同性の友人サリーに恋心を抱いていた18才のあの夏・・・
ピーターはその朝偶然インドから帰国し、彼女のパーティーに出席する。
彼は、若き日に愛した彼女を見つめながらこう思う。
銀色がかった緑色のドレスを着て、人々の間をすべるように歩いていく上品で美しいクラリッサ。
でも、そんな彼女にも老いが確実に近づいている。
晴れあがった夕暮れの、波間に沈んで行く夕陽を、手鏡の中に映し出してながめている人魚のよう・・・昔は虚勢に満ちていた彼女も今は仄かに漂う優しさがあるのみだ。
でも遠い日・・・彼女は自分を捨てた。理性と打算から自分を捨てたクラリッサ・・・それを思うと耐え難い思いが甦ってくる。
1923年6月半ばの水曜日のロンドン、この1日がこの小説の舞台だ。
ジェイムズ・ジョイスの『ユリシーズ』の影響を受けて書かれたというこの小説は、朝に花を買いに行く場面から始まり、深夜にパーティーが終るところで締めくくられる。
作者ヴァージニア・ウルフは1882年、ロンドンで評論家レズリー・スティーブンと妻ジュリアとの間に生まれた。
若い頃に両親と兄を相次いで亡くすという不幸、父の先妻の兄弟との近親相姦や同性愛的な傾向などに対する悩みは、彼女の繊細な心に病的な影を落とした。
ヴァージニアの兄トービーを中心に発足した「木曜会」(後にブルームズベリー・グループと呼ばれる)は知識人の出入りする集まりで、兄亡きあと、ヴァージニアと姉とで続けられた。
1912年ライフデザイン評論家のレナード・ウルフと結婚。
1919年にロンドンの南約70キロに位置するロドメルのモンクス・ハウスを手に入れ、1924年ホガース出版を手掛けたリッチモンドの家を引き払い、全面的にロドメルに移り住んだ。
 今はナショナル・トラストの管理下にあるその家は、鄙びた村の一角にある。 今はナショナル・トラストの管理下にあるその家は、鄙びた村の一角にある。
門を開けて庭へ回り、石段を数段上るとヴァージニアが寝起きしていた書斎だ。
1941年3月28日の朝、周囲の人たちが目を離したすきに、彼女は遺書を残してこの部屋から出て行き、コートのポケットに石を沢山詰め込んで、ウーズ河で入水(じゅすい)自殺した。
庭の花壇の端にはかつて2本の楡の木があり、レナードとヴァージニアと呼ばれていたという。
ウルフ夫妻の遺言でそれぞれの木の下に彼らの亡骸は灰となってまかれた。
しかし1本は強風で倒れ、残った1本も枯れてしまったという。
垣根越しに見える古い教会の塔の上を、眩しい白雲が渡っていく。
 私がリッチモンドに住み始めて、もう5年だ。 私がリッチモンドに住み始めて、もう5年だ。
6月の青葉は輝き、風は光の粒子を天に巻き上げる。
この町にヴァージニアとレナード夫妻が1915年から1924年まで住み、その間1917年にホガース出版を始めたという家がある。
家は長屋形式だが、なかなか立派な趣だ。
ここを通るたびに私はちょっと立ち止まり、ブルー・プレイクを読まずにいられない。
地下室から印刷機を回す音が聞こえ、インクのにおいが漂ってくるような気がする。
リッチモンドを歩きながら、私は時折り幻のように彼女の姿を見る。
雑踏の中の後ろ姿、テームズ川の辺(ほとり)を夫と共に散歩するシルエット、リッチモンド・ヒルに佇み遠い町を見下ろす横顔、そして冬の日に素敵な黒い帽子を目深に被り、灰色の長いコートを着てバスに乗り込んで来る、そんな姿を・・・
かつて彼女が住んだ教会の前の坂道を横切りながら、私は思う。
このすべてのなかに、私の愛するものがある、と私は言えるだろうか。
人生、ロンドン、6月のこの瞬間・・・なぜ人がこれほど人生を愛するのか、誰も知らない・・・と。 |