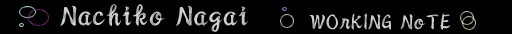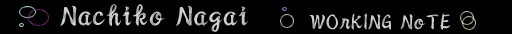黒いレースのような枝を広げた冬木立の中、サーペンタインの池を右手に見ながら歩いていく。ロンドン、ハイドパークの一隅、細い鉄柵に囲まれたバード・サンクチュアリー(鳥の保護区)に、リーマの像がひっそりと建っている。小説『緑の館』の作者ハドソンを記念してつくられたエプスタイン作のレリーフだ。両手を広げて鳥を呼び集めているリーマの像が苔むした石に浮き彫りされている。 黒いレースのような枝を広げた冬木立の中、サーペンタインの池を右手に見ながら歩いていく。ロンドン、ハイドパークの一隅、細い鉄柵に囲まれたバード・サンクチュアリー(鳥の保護区)に、リーマの像がひっそりと建っている。小説『緑の館』の作者ハドソンを記念してつくられたエプスタイン作のレリーフだ。両手を広げて鳥を呼び集めているリーマの像が苔むした石に浮き彫りされている。
像の傍らの枝で鳴き交わしていた尾の長い明緑色のオームが、何かの物音に驚いていっせいに飛び去っていった。暗いロンドンの空に舞う南国の鳥は、鮮やかな残像を目の内に残して心なしか孤独な風情だ。見上げる天に冷たく凍えそうな風が吹きすぎる。
少女の頃読んで、心から感動した物語は、初めての恋に似て忘れ難いものだ。私にとって、ハドソンの『緑の館』は、まさしくそのような物語のひとつだった。今でもその時の気持ちを思い出すと、喉の奥がちょっと痛くなって胸が一杯になる。
当時まだ小学生だった私は、1週間あまりのあいだ、家族と口をきくのさえも億劫なほどその本に魅せられていた。表紙に儚げな少女の絵が描かれた白い装丁の単行本だった。
私は、毎日学校から帰ると世界地図を広げて、南米のベネズエラ周辺にじっと目を凝らす。するといつしか心は、色鮮やかな鳥や、木々の上で生活する珍しい動物を見あげながら、オリノコ河上流の密林をさまよっているのだった。
南アメリカ、ヴェネズエラの名門出身の青年アベルは、国内の政治動乱を機に祖国を離れ、オリノコ河の南部、ギアナ地方の奥地へと入っていく。彼にとって熱帯の密林は憧れであり、そこに住む未開の人々にも興味を抱いていた。
先住民の部落に住み着いたアベルは、ある日、魔性の女が住むと畏れられている森に向かう。そこで彼は、鳥の鳴き声に似た神秘的な言葉を話す美しい少女に出会う。
ある日、毒蛇に噛まれたアベルが少女に助けられたことから、ふたりは親しさを増していく。ヌフロ老人と共に暮らす少女の名はリーマ、アベルは祖国で馴染んでいた女性とはまるで違う、今までに会ったことのない、野生の、それでいて儚げな少女に、心を奪われてしまう。やがてふたりは激しい恋に落ちる。
リーマは自分が生まれた土地リオラマへ行きたいと強く希望する。リーマの旅の目的は、彼女の恋心を理解してくれるはずの同胞を捜すことだった。しかし彼女の一族はすでに死に絶えていた。あたかも妖精のようなリーマは、かつて自然と一体になり穏やかに暮らしていた種族のたったひとりの生き残りだったのだ。
絶望するリーマ、しかしアベルの愛をしっかりと受け止めて、私の知りたいことは本当は全部あなたの中にあった、と告げて、彼女はひと足先に森へと戻っていく。アベルとの結婚のために花嫁衣裳を作って彼を待とうと森への帰り道を急いだのだ。ふたりが出合った熱帯の大密林は、彼らの幸せな「緑の館」となるはずだった。
しかし、リーマは森で待ち伏せしていた先住民たちに襲われ、無残にも焼き殺されてしまう。アベルはそれを知って復讐の鬼と化し、策略を廻らして先住民一族を皆殺しにする。ひとり「緑の館」で孤独な日々を過ごした彼は、やがて悲しみから立ち直り、リーマの遺骨を拾って、故郷の町へと帰っていく。
 ウィリアム・ヘンリー・ハドソンは、1841年アルゼンチンのブエノス・アイレスの郊外キルメスに生まれた。南米で過ごした少年時代の様子は、1917年、彼が77歳の時に出版された『はるかな国、とおい国』という自叙伝に書かれている。1874年イギリスに渡り、1876年に20歳近く年上のエミリーと結婚してロンドンに落ち着いた。ハドソンは1900年にイギリスに帰化し、1922年、前年に他界した妻を追うように81歳でこの世を去った。 ウィリアム・ヘンリー・ハドソンは、1841年アルゼンチンのブエノス・アイレスの郊外キルメスに生まれた。南米で過ごした少年時代の様子は、1917年、彼が77歳の時に出版された『はるかな国、とおい国』という自叙伝に書かれている。1874年イギリスに渡り、1876年に20歳近く年上のエミリーと結婚してロンドンに落ち着いた。ハドソンは1900年にイギリスに帰化し、1922年、前年に他界した妻を追うように81歳でこの世を去った。
『Green Mansions・緑の館』は1904年に出版された。鳥類研究家でもあったハドソンは、この小説でリーマを美しい熱帯のハチドリに喩え「the
bird girl」と呼んでいる。
ハドソンの自然に対する深い造詣、それを伝える文章のなんと思い遣りに満ちていることだろう。ハドソンは博物学者だったが、死んだ標本よりも生きているものの姿を慈しんだ。それゆえに彼はアルコール漬けの死骸や剥製を嫌悪していたという。
今から100年ほど前に書かれた『緑の館』・・・春の一時を除いて、常に暗いモノトーンのイギリスの風景のもと、生まれ故郷の光り輝く原色の世界を懐かしむとき、そこに明らかな生命の芽生えと成長を感じたに違いない。
すでに100年も前、現在の熱帯雨林の伐採を予言したかのようなこの悲恋物語、リーマは滅び行く自然そのものの象徴だったのかもしれない。
植物、動物、生きとし生ける者すべてを愛する慈悲の眼差し・・・この優しさは哀しみの旋律を帯びて、リーマの最期の場面へと繋がっていく。リーマの死は先住民の口からアベルに告げられるだけで、現実の場面としてえがかれてはいない。
リーマを失い、森の中で孤独な生活を続けるアベルが、ある夜、小屋で火を焚いていると、1匹の白い蛾が彼の手にとまった。高雅な趣の蛾は、アベルの手から天井に飛び上がると、焚き火の中に真逆さまに落ちて焼かれてしまう。
その華麗な、しかし残酷な場面は、大木に逃れたリーマが先住民に火をかけられ、はるか高みから撃たれた鳥のように落ちていく姿を連想させる。少女の私はこの焚き火の場面で、リーマの最期を目の前にまざまざと見せつけられる思いがしたものだ。リーマが本当に死んだのだという実感・・・もう取り返しがつかない、この世で最も美しいものを失ったという感じを伴いながら・・・
 2006年、新年、捜し当てたその家は人通りのない街角にひっそりと佇んでいた。ここはロンドンのノッティング・ヒルの北、年上の妻と暮らし、家をフラットに改装して生計をたてていた家だ。そしてハドソンはここで終焉を迎えた。 2006年、新年、捜し当てたその家は人通りのない街角にひっそりと佇んでいた。ここはロンドンのノッティング・ヒルの北、年上の妻と暮らし、家をフラットに改装して生計をたてていた家だ。そしてハドソンはここで終焉を迎えた。
玄関脇の白壁に彼が生まれ育ったキルメスの家がレリーフされた版が嵌り、その足元に、枯れ葉が身を寄せ合うように吹き溜まっている。
一瞬、幻のオームのけたたましい鳴き声が灰色の雲を引き裂き、寒さで丸まった冬の落ち葉の上に、強烈な南国の陽射しを投げかけたような気がした。冬の落ち葉はこんな午後、激しいスコールの行き過ぎた密林の奥で、キラキラと煌めく大きな雨だれを、ポタリポタリと受けとめる白昼夢を見るのかもしれない。 |