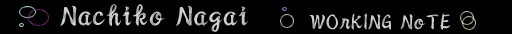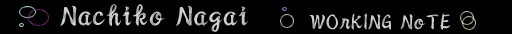|
居間の窓辺に座って、庭伝いに広がるリッチモンド・パークの森を眺めながら、私は、遠い日本を思い出す。
イギリスの女達の悲しみを覆う服喪(ふくも)のベールのように、黒く縺(もつ)れ合った小枝を広げた木々が、寒風に晒されて凍えたようにたち尽くしている。
灰色の空から木枯らしが私の心の奥まで吹き込んで、忽(たちま)ちのうちにこの身をさらい、時間と空間を飛び越えて遥かな東の国へと運んでいく。
シベリアの空の上から日本海を渡り、眼下に日光連山、長野、群馬の山波を、さらにその先に霞む雪に覆われた富士の山を見ながら、やがて茫漠とした冬の関東平野の上にさしかかる。
武蔵野の冬枯れの雑木林がうねるように果てしなく続き・・・もう、そこは夕暮れ・・・なだらかな多摩丘陵の頂(いただき)から白い細かい雪が降りだし、地の果てから這い登る宵闇が、幽かな残光の大気を刻一刻と夜の淵へと絡めとっていく。
雪は降り止まず、風は益々激しく吹きすさび、それは真っ白な炎の渦巻きとなって、すでに暗幕に包み込まれた森を焼き尽くすかのようだ。
泣き叫ぶ吹雪の音が、私の心を呼び寄せる祖国の声のように、幾度も幾度も繰り返し響き、久遠(くおん)の鐘の音(ね)のように鳴り止まない。
凛々しい若者、巳の吉は、すざましい吹雪の夜この世のものではない美しい女に出会う。
女は、一度(ひとたび)息を吹きかけられれば血も凍りついてしまう雪の化身であった。
女は巳之吉に近づいたが、ふと思い留まり、まだ若いのだから命を助けてやろう、この事は誰にも話してはいけない、話せば命がないと言い残して去っていった。
次の年の冬、巳の吉は江戸へ向かう旅の途中だという若い娘に出会い、気に入って妻にした。
お雪という名の色の白い美しい女であった。
お雪は姑にも優しくつかえ、10人の子供を産んだ後も少しも年をとらなかった。
ある夜、巳之吉はお雪の顔を見ながら何気なく、18歳の年に吹雪の夜に出会った美しくも恐ろしい女の話をしてしまう。
お雪は巳之吉のそばへ来ると、それは私だと言い約束を破った事を責め、命だけは助けるが子供達を大切に育てるように言い残し、白く煌く霧となって、消えてしまうのであった。
『雪女』は「怪談」の中に収められている物語である。
「怪談」は「不思議なことの物語と研究」という副題がつけられており、序文には多くのものは日本の古典の中から採ったものであるが、『雪女』は調布村の農夫が西多摩の民話として語ってくれたものとしている。
作者ラフカディオ・ハーン(日本名、小泉八雲)は、1850年に生まれた。
父はアイルランド人、母はギリシャ人で、ハーンが4歳の時両親は離婚した。
少年時代をアイルランドのダブリンで過ごしたハーンは、その後世界中を放浪して、39歳の時雑誌社の特派員として日本へ渡った後、松江中学の英語教師の職を得、節と結婚して松江で暮した。
その後熊本へ、それから神戸、東京へと居を移し、1904年に54歳でこの世を去った。
ハーンは長い鎖国の間に培われた純粋な日本的なものに愛着を感じ、古典にも親しみ、多くの日本文化紹介の書物を残した。
また、民話や伝説、物語など、特に不思議な話、不思議な現象に興味を持ち、周囲の人々の語る沢山の物語を熱心に収集した。
同じアイルランド人のイエイツが祖国を愛し祖国の民話を集めたのに対し、ハーンは遠い異国、日本の民話に郷愁を感じたのだろうか。
しかしこれらハーンの書いた物は、欧米人の読者のために書かれたもので、文中の距離や長さの単位がマイルやインチとなっている。
明治のお雇い外国人最後の人と言えるハーンは、東京帝大の講師の座を、ロンドンから帰国した新任の夏目金之助(漱石)に追われるような形で退いたが、生徒達の敬愛は深く、彼らはハーンの留任運動を起こした。
しかし明治維新、文明開花の混乱も静まった当時の日本の状況から推すれば、政府は高額な給料を支払わなくてはならない外国人教師よりも、海外留学から戻ってきた日本人教師に委ねたかったのであろう。
 昨年の夏の終わりに私達はアイルランドへ旅行をした。
昨年の夏の終わりに私達はアイルランドへ旅行をした。
大きな古墳の丘を取り巻く風ばかりが吹き過ぎる草原、筒型の高い塔の上を飛ぶ黒い鳥の群、廃墟の教会の庭に傾く摩滅した石の十字架・・・繊細なケルト模様が施された湿った遺構の影には、誇り高い妖精たちが息を潜めてじっとこちらを見つめているのだろうか。
神秘の国、アイルランド・・・私達は、キラーニーの町はずれにある古いホテル、マナーハウスに泊まった夜のことを思い出す。
夜明け前の闇はどこまでも深く、この世は全てが死に絶えたかのような静寂の原野だった。
寝つかれぬ耳に、長く暗い廊下の果てから、ギシ、ギシ、ギシ、と人の歩く音が近づいて来た。
足音は次第に大きくなり、厚い部屋のドアを通り抜けて、すぐ耳元で轟音となって鳴り響き、また引き返すような感じで少しずつ弱まりふと途絶えたのだった。
そこは、建物の最上階にある裏庭に面した角部屋だった。
小さな窓の外には果てしなく荒地が広がり、窓枠に食い込むように茂った蔦の葉が、早くも真っ赤に色づいていた。
アイルランドでは生と死の狭間にさまよう、神に召される事のない魂の仕業だと考えるのだろうか。
このようなアイルランドの風土は、文学者としてのハーンに、大きな影響を与えた事であろうと思わせる不思議な出来事だった。
ハーンはまた、虫に題材をとった不思議な話を数多く集めている。
蝶、蚊、蟻について書かれた「虫の研究」と題する随筆があり、昆虫の大好きな私は、それをとても興味深く読んだ。
そのような小さな虫に対する思い遣りや感じ方、それに関する物語や伝説などを見ると、最もその民族の心根が現れるような気がしてならない。
『蝶』の話の中に心惹かれる小さな物語がある。
東京近郊のある寺の墓地裏にひとりの老人が、およそ50年も住んでいた。
人柄も良く普通の生活をしているのに、決して女性に目を向けようとせず、独身を通していた。
ある年の夏、ついに病に倒れ死期が近づいたので、親戚の者が集まると、老人が静かに眠っている部屋に、大きな白い蝶がひらひらと舞い込んできて、その枕にそっと止まった。
追ってもまた舞い戻ってくるので、親戚の者は不思議に思って蝶について行くと、きれいに手入れをされた墓石の前でふと消えてしまった。
そこには18歳で亡くなった、聞いた事もない女性の名が刻まれていた。
部屋に戻ると老人はもう息をしていなかった。
やがてそれは老人の若い頃の許婚(いいなずけ)の墓であったとわかる。
彼は彼女の墓の傍で、供養をしながら生きてきたのだ。
そして長い歳月を待ち続けた彼女の魂は、終(つい)に純白の大きな蝶になって彼を迎えにきたのだった。
この世には存在しない筈の白という色。
白とは色ではなくひとつの美・・・それは純潔の証しだ。
そしてまた、白は静かな哀しみに満ちた無・・・それは死に他ならない。
好きな男の妻になるために、別の世から人間の娘となってやってきた雪の化身。
そして、ひたむきな愛を貫き、真っ白な蝶になって愛する人の枕辺に迎えにきた娘の魂。
漆黒の闇に流離(さすら)う憐れな者達は、いつしか仄の白い堤燈のあかりに導かれて、ひたひたと通り過ぎていく声のない葬列となって、行く手に幽かに見え始めた慈悲の光に向かって進み、闇の果て、彼岸の淵に沿って咲く白蓮の彼方へ、揺らめきながら霞みのように消えていくのだろう。
*ダブリンはアイルランドの首都。
*ハーンの墓は、東京、雑司が谷墓地のある。
|